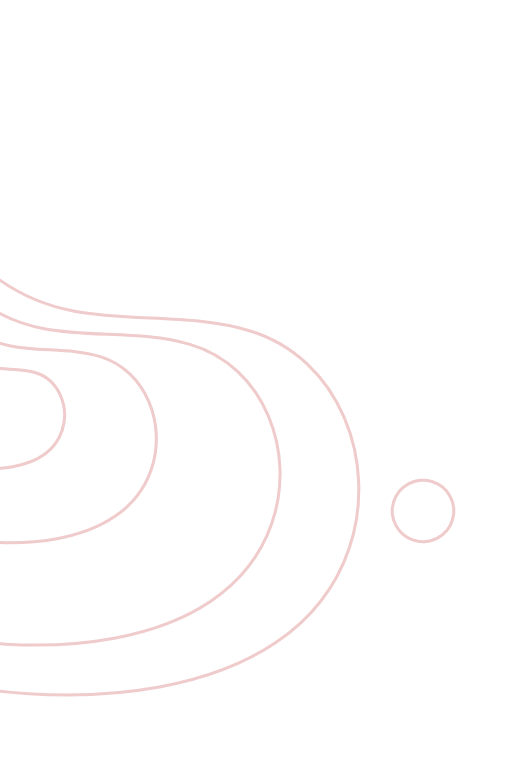FAQ
FAQ
FAQの使い方
細胞培養食品に関する理解を深めていただくため、よく聞かれる質問と回答についてまとめました。
関連技術の進展や各種制度の動向などを踏まえて、随時更新していきたいと考えております。したがって、このFAQの利用に当たっては、当サイト(クラフトエッセン.com)において、最新のものを確認していただくようにお願いします。
検索キーワードを入力するとキーワードを含むQ&Aを絞り込むことができます。なお、画面右上にある「FAQ」をクリックすると、絞り込みを解除できます。
基本・総論関係
動物組織から細胞を採取し、栄養素(ブドウ糖、アミノ酸、ミネラル等)を含む培養液とバイオリアクターと呼ばれる装置を用いて増やすことで作られます。一般的には、収穫された細胞培養食品を素材として加工食品の形で、製造・利用されます。
細胞培養食品は環境コントロールが比較的容易で地球温暖化等への対応力の面で優れており、新たな食資源になる可能性があります。
環境負荷の軽減に貢献し得るポテンシャルがありますが、そのためには、より効率的な生産体系の確立、すなわち、①良好な増殖性を示す細胞の選定や作出、②製造施設の大規模・自動化、③培地の低コスト化、などの技術的な課題をクリアしていくことが必要になります。
通常、細胞は生体から取り出すと死んでしまいますが、適切な環境(温度、栄養、湿度、酸素濃度等)で育てることで、生体外で増やすことできます。こうした技術を「培養」と言います。採取した細胞は、無菌的かつ適切な環境下で、栄養や酸素が含まれた培養液の中で育てています。
動物(有精卵等)から採取した細胞を原料とし、培養技術によって生産した新しい食品素材(Novel food: ノベルフード)で、「培養肉」や「細胞性食品」と呼ばれることもあります。
細胞培養食品の特徴
細胞培養食品は動物由来の細胞を「培養」することで製造されますが、大豆ミートなどの植物性の代替肉は植物性タンパク質を「加工」することで製造されます。
また、細胞培養食品は動物性たんぱく質を含んでいるため、植物性の代替肉とは異なる栄養や風味が期待されています。
現在、国内で開発が進められている家きん細胞培養食品は水分量の多いペーストの状態で収穫されるため、他の素材と組み合わせた加工食品としての利用が想定されます。なお、どのような素材と組み合わせて、どのように調理するかによってその味や食感は大きく異なり、新たな食材として利用方法の検討が進められております。
栄養・安全性関係
細胞培養食品は製造方法にもよりますが、科学的には、食品としての安全性を十分に確保した形で生産することができると考えられます。細胞培養食品の安全性は、一義的には製造者によって確保、担保される必要がありますが、世界的には、国による何らかの安全性確認も必要であると認識されております。
日本における細胞培養食品の安全性確保について、消費者庁を中心に国の規制部局が各界の専門家などの意見も聴きながら検討を進めております。細胞培養食品の安全性を確保するための枠組みについては、未だ定まっておりませんが、国が何らかの方向性を示すことが見込まれるため、それに従って安全性を確認した後、日本における細胞培養食品の提供が可能になると考えております。
現在、国内で開発が進められている家きん細胞培養食品については、原材料は全て食品と食品添加物を用い、細胞は遺伝子組換えなどをしていない通常の細胞であり、通常の食品と大きく異なる安全上のリスクはないと考えられますが、国が策定を進めている細胞培養食品の安全確認手続に申請することを予定しております。
なお、細胞培養食品の製造工程では、異状の有無をモニタリングするとともに、最終製品を加熱殺菌した上で冷凍保存し、ロット毎に製品検査を実施しております。
基本的には、使用する細胞や培地などの原材料に則したアレルギーがあると考えられ、例えば、家きん細胞を使用していれば、家きん肉のアレルギーのリスクが想定されます。
いずれにしろ、細胞培養食品については、従来の食品と同様にアレルギー試験を行い、アレルゲンが確認された場合は、通常の食品と同様に製品ラベルに記載することになります。
どの細胞を使うかのか、どの細胞と比較するかにもよりますが、従来の食肉と比べて大きな差はないと考えております。(肝臓細胞の場合、胸肉やささみに近い栄養成分)
培養・製造関係
使用する細胞や培養システムによって大きく異なりますが、細胞培養食品の素となるタネ細胞の準備に数週間、バイオリアクター装置を用いた拡大培養に1~3週間程度の時間が掛かると言われています。
動物や細胞の種類によって、必要な栄養素や培養環境が異なるため、全ての細胞が培養できるわけではありませんが、様々な動物の細胞に関して、培養に成功した事例が報告されています。
現在までに、家きん類(ニワトリ、アヒル、ウズラ)、哺乳類(ブタ、ウシ)、魚類(サーモン、ウナギ、タイ)などの細胞について、細胞培養食品の開発が報告されています。
培地には、糖類(ブドウ糖)、アミノ酸、ビタミン、ミネラルなど、細胞の生存や成長に必要な栄養素が含まれます。さらに、現在、食経験の食品あるいは食品添加物のみで構成された食品グレードの培地の開発も進んでおります。
足場とは、バイオリアクター装置内などで細胞が接着し、増殖するための基盤(土台)になる素材のことを言います。その中でも、食べられる素材で作られた足場は「可食性足場」と呼ばれ、食経験のある食品あるいは食品添加物のみで生産されているため、基本的な安全性は担保されていると考えられます。
細胞培養食品の一般的な原料としては、タネ細胞、基礎培地、成長因子、血清代替などが挙げられます。
また、バイオリアクター装置を用いた拡大培養工程においては、可食性(食べられる素材から作られた)の足場材を使用することもあります。
2013年にオランダのマーク・ポスト教授らが、世界で初めて細胞培養食品を用いたハンバーガーを作製した際は1個で約3000万円の製造コストがかかったと言われていますが、現在の製造コストは、技術的な進展によって、100 g当たり数千円から数万円と試算されています。
一般的な食品と比べて、依然として高い製造コストであり、効率的な細胞培養技術の開発に加えて、成長因子や基礎培地などの原材料関係のコストダウンなどにより、製造コストを大幅に下げる必要があります。
細胞培養食品の生産には、細胞培養装置(クリーンベンチや顕微鏡など)、バイオリアクター装置(バイオリアクター、センサー類、滅菌システムなど)、加工装置(収穫装置、包装・充填機など)、保管設備(冷蔵庫、冷凍庫)などの施設が必要になります。
世界各国で細胞培養食品の製造方法に関する研究が進められておりますが、一般的には以下のような流れで生産されます。①動物組織から細胞の採取して保存
②細胞の品質確認
③細胞、基礎培地、成長因子、足場材などを充填したバイオリアクターで、培養環境をモニタリングしながら拡大培養
④培養液を洗い流し、増殖した細胞を収穫
⑤細胞培養食品を原料として加工食品などを作る
環境負荷・持続可能性関係
細胞培養食品は動物の細胞から作られ、理論的には環境負荷を抑えた形で生産できる可能性があり、タンパク質クライシスや食料問題の解決に貢献し得るポテンシャルがありますが、そのためには、より効率的かつ大量生産が可能な細胞培養技術や低コストな培地製造技術の確立が必要になります。
細胞培養食品は、食肉の代わりと言うよりは、新たな食材として捉えた方が良いのではないかとの認識が広がりつつあります。
細胞培養食品が普及していくためには、効率的な製造を可能とする生産インフラの開発や細胞培養食品の特徴を活かしたメニューや加工食品の開発が課題になりますが、さらなる研究開発が必要な状況です。
理論的には、資源の利用効率が高いため、持続可能な食料供給を支えるための選択肢になり得る可能性がありますが、現状は環境負荷が低いとは言えない段階です。
環境負荷を下げるために、より効率的な培養生産体系の確立、すなわち、①培養に適した細胞の選定や作出、②製造施設の大規模化や自動化、③穀物資源に頼らない培地の開発などの技術的な課題をクリアしていく必要があります。
販売・物流関係
世界各国で細胞培養食品の開発が進んでいますが、政府による安全性確認が完了し、実際に食べられるようになった国は、シンガポール、米国などごく一部です。
日本では、消費者庁において細胞培養食品の安全性確認の枠組の検討が進められているところで、今後、安全性確認に関する何らかの手続が制定されると見込ますが、細胞培養食品の事業者が安全性に関する資料を添えて申請して手続を完了した後に日本でも食べられるようになる思われます。
細胞培養食品については、まだ安全性確認の枠組が検討されている段階で、実際に流通や輸入することは困難な状況です。なお、輸入に当たっては、食品としての安全性に加えて、動物検疫の面でも問題がないことを確認する必要が生じると推察されます。
日本で流通する食品については、食品表示法に基づいて適正な表示が義務付けられております。細胞培養食品については、まだ安全性確認の枠組が検討されている段階で流通はまだ先の話になりますが、消費者が購入する際に細胞培養食品であることがわかるような形で表示されると思われます。
なお、クラフトエッセンについては、既にロゴマークも作成しておりますが、実際に販売する際には、消費者が間違うことがないようなわかりやすい食品表示を実践していきます。
官能評価会は、開発関係者のみによって行われる製品の品質や嗜好性を評価するための会で、食品や飲料の開発過程で行われます。それに対して、試食会は不特定多数の方に製品を試していただくための会で、官能評価会と試食会では、目的、対象者ともに異なります。
細胞培養食品に関しては、今後、国が制定すると見込まれる安全性の確認プロセスを経た後、レストランのメニューや加工食品などの形で提供・販売されると見込まれております。
いずれにしろ、現時点では、通常の食品と比べて、製造コストが高いこともあり、その生産・流通量はかなり限られた形になると見込まれます。