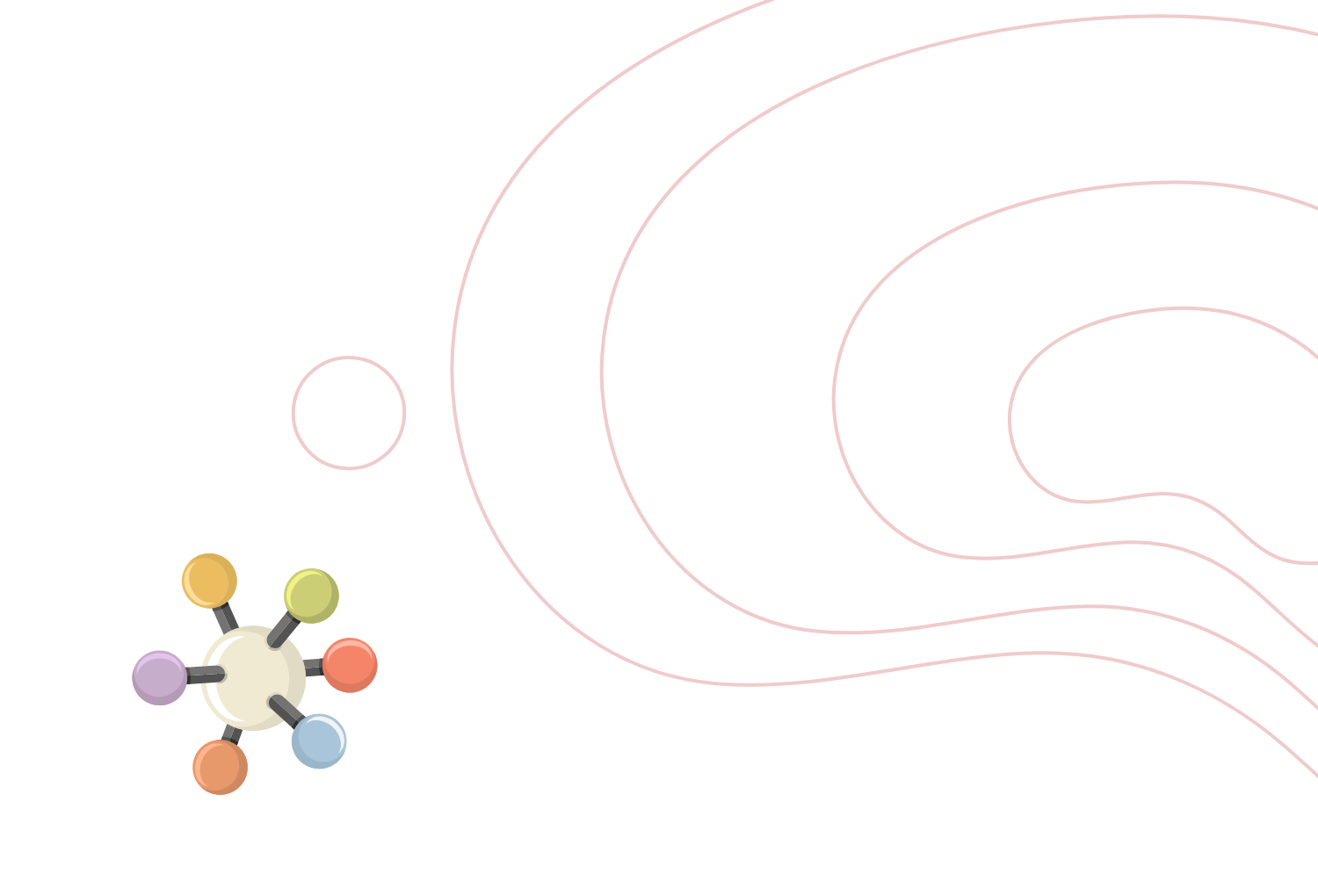用語集
glossary
あ行
-
案内(用語集の使い方)
細胞培養食品に関する理解を深めていただくため、よく聞かれる用語について、できるだけわかりやすくまとめました。
関連技術の進展や各種制度の動向などを踏まえて、随時更新していきたいと考えております。
したがって、この用語集の利用に当たっては、当サイト(クラフトエッセン.com)において、最新のものを確認していただくようにお願いします。
キーワードを入力して検索ができますが、検索を終了する際には、画面右上にある「用語集」をクリックしてください。 -
RNAシークエンス(RNA sequence (RNA-seq))
細胞内のRNAを網羅的に解析する技術。細胞や組織における遺伝子発現量を網羅的に測定することで、細胞の状態を評価、比較することが可能になる。
-
ISO規格(International Organization for Standardization (ISO))
日本国内で一般的な食品関連のISO規格はISO9001(品質保証), ISO14001(環境), ISO22000(食品安全)等が有り、上記規格を導入することで、より総合的なマネジメントシステムを構築することが可能。
-
iPS細胞(iPS cells)
iPS (induced pluripotent stem cells:人工多能性幹細胞)は、体細胞(皮膚や血液等の細胞)に特定の遺伝子を導入することで、体のあらゆる細胞に分化できる能力を獲得した細胞。
-
I-MEM(アイメム)(Integriculture-minimum essential media (I-MEM))
創薬や再生医療等のバイオ産業で広く使われている細胞培養用溶液である最小必須培地(Minimum Essential Media:MEM)を、独自に食品原料のみで再構成した基礎培地。細胞培養に欠かせないアミノ酸や糖類を、食品として認可されている成分のみで構成している。
-
足場材(Scaffold)
バイオリアクター内等で、細胞が接着し、増殖するための基盤(土台)になる物質。その中でも、食べられる素材で作られた足場は、「可食性足場」と呼ばれている。
-
アニマルフリー(Animal-Free)
動物を使用しない製品やプロセスを指します。培養肉の場合、動物を屠殺せずに製造される点が該当します。
-
一般財団法人バイオインダストリー協会(Japan Bioindustry Association)
科学技術の成果の産業化推進、産業基盤の充実と国際競争力の強化を目指し、政策提言・政策対話、先端バイオ関連情報の提供、オープンイノベーションの推進、国際ネットワークの形成を通して、バイオインダストリーの発展や基盤整備に向けた活動を行う団体。
-
SOP(Standard operating procedure (SOP))
企業内や組織内で、特定の業務を遂行するための手順を標準化し、文書化したもの。作業ミスを減らし、一貫した品質や安全性を確保するために使用されている。
-
エピジェネティクス(Epigenetics)
遺伝子の塩基配列そのものは変わらないまま、遺伝子の働き方やオン/オフが変化する現象。
-
FSSC22000(Food Safety System Certification 22000)
ISO22000をベースに、より確実に食品安全管理を実施するためのマネジメントシステムで、ISO22000で規定されている要求事項、前提条件プログラム、追加要求事項の3つから構成されている。
-
FBS(Fetal bovine serum)
ウシ胎児の血液から採取された血清成分のことで、成長因子やアルブミン等のタンパク質を含んでいます。細胞培養において、最も広く使用されている培養添加物の一つです。
-
オミクス解析(Omics analysis)
生物の持つ膨大な遺伝情報や、その遺伝情報に基づいて作られる様々な分子(タンパク質、代謝物など)を網羅的に解析する技術の総称。具体的には、トランスクリプミクス(RNA)、プロテオミクス(タンパク質)、メタボロミクス(代謝産物)、エピゲノミクス(DNAメチル化)解析等が実施される。
か行
-
拡大培養(Expansion culture)
前培養工程で増やした細胞、足場材、バイオリアクター等を用いて、細胞を効率的に増やし、細胞培養食品等を生産する培養工程。
-
カルネットコンソーシアム(CulNet consortium)
インテグリカルチャー及び様々な領域で高い技術力を有する企業が参画する細胞農業のオープンイノベーションプラットフォームで、その目的は、培地、足場、培養装置などの課題を解決し、細胞農業のサプライチェーンの構築。
-
カルネットシステム(CulNet system)
生体内では多様な細胞が成長因子等を産生し、血液循環することで、各組織において細胞の増殖や分化が制御されている。カルネットシステムは、こうした臓器間相互作用を生体外で模倣する循環型バイオリアクターシステムであり、細胞の増殖や分化に必須な成長因子等の作出に活用されている。
-
環境負荷(Environmental burden)
人間の活動によって環境に加えられる影響の中で、環境保全上の支障の原因となる恐れのあるもの。
-
環境負荷評価(Life cycle assessment)
製品やサービスが環境に与える影響を調査・予測して定量的に評価する手法。
-
幹細胞(Stem cells)
生体内の存在する細胞の中で、自己複製能(自分と同じ性質を持つ細胞を複製する能力)と分化能(自分と異なる性質を持つ細胞に変化する能力)という2つの特徴を持つ細胞。
-
官能評価会(Sensory evaluation test)
人間の感覚を利用して製品の品質や嗜好性を測定するために用いられる評価方法で、食品や飲料の開発過程で行われることが多い。なお、不特定多数を対象とした「試食」とは異なる。
-
基礎培地(Basal medium)
細胞の培養に必要な最小限の栄養素(糖、アミノ酸、無機塩類等)を含んだ培地で、通常は成長因子等を添加して使用される。
-
クリーンベンチ(Clean bench)
ゴミ、ホコリ、浮遊部生物等の混入を防ぐために、一定の清浄度レベルになるように管理された装置。適切な管理及び作業手順により、試料を無菌状態で扱うことが可能になる。
-
継代(Passage)
細胞を増殖するため、培養容器等で培養した細胞を新しい培養容器に移し替える作業。
-
血清成分(Serum)
血液から凝固因子を除いた液体成分で、様々なタンパク質やその他の物質を含んでいます。通常の培養では、牛胎児血清(Fetal bovine serum: FBS)が使用されることが多い。
-
抗生物質(Antibiotics)
細胞培養工程等で微生物の混入や増殖を防ぐために用いる物質。微生物の細胞壁やタンパク質の合成等を阻害することで、微生物の増殖を抑制します。
-
酵母エキス(Yeast extract)
酵母を原料として、その成分を抽出・濃縮した物質。アミノ酸、ビタミン、ミネラル等の栄養素を含んでおり、微生物や動物細胞の培養添加物として用いられる。
-
コーティング剤(Coating solution)
特定のタンパク質、ペプチド等を用いて培養容器の表面をコーティングし、培養容器表面への細胞の接着性を向上させ、増殖しやすくするための成分。
-
コンタミネーション(雑菌汚染)(Contamination)
細胞培養工程や製造工程等で、意図せずに微生物が混入することを言う。略して「コンタミ」と呼ばれることも多い。
さ行
-
再生医療(Regenerative medicine)
病気やけがで機能不全に陥った生体組織や臓器に対して、健康な細胞等を利用して損なわれた機能の再生を図る医療。
-
細胞株(株化細胞)(Cell line)
初代培養細胞の形質転換や不死化等の操作により、無限に増殖できるようになった細胞の集団。
-
細胞集団倍加数(Population doubling level)
細胞集団がこれまでに分裂してきた回数を累積値として表した数値。 初代培養細胞等の有限分裂の性質がある細胞は、おおよそ50PDL(細胞の分裂回数)を超えると老化の傾向を示す。
-
細胞凍結(Cell cryopreservation)
細胞を長期間保存するために、液体窒素等を用いて超低温で冷凍します。この技術により、同質の細胞を大量に調製し、保存や輸送することが可能になり、凍結細胞の集団は「セルバンク(細胞バンク)」と呼ばれている。
-
細胞農業(Cellular agriculture)
動物や植物の細胞を培養することで、細胞培養食品を始めとする人にとって有用な資材を得る技術及び産業。
-
細胞農業研究機構(Japan Association for Cellular Agriculture (JACA))
国際的に感心が高まってきた細胞農業に着目し、食料安全保障や持続可能性をはじめとする日本の重要課題へ貢献するため、日本として細胞農業に対してどのように向き合うべきか、戦略の立案から社会実装までを目的とする団体。
-
細胞培養加工食品(Cell-cultivated processed food)
細胞培養食品を原料として製造された加工食品。
-
細胞培養食品(Cell-cultivated food)
動物個体等から抽出した細胞を原料とし、細胞培養の技術を用いて生産した食品素材。培養肉(魚)や細胞性食品とも呼ばることもある。
-
細胞剥離剤(細胞分散液)(Cell dissociation solution)
フラスコ等の培養容器に接着している細胞を剥がすために用いられる液体成分。通常、細胞間及び細胞と培養容器間の接着に関わるタンパク質を切断(分解)するために使用される。
-
細胞播種(Cell seeding (Cell plating))
フラスコ等の培養容器、またはリアクター装置等に細胞を投入する操作のことを言う。
-
細胞融解(Cell thawing)
凍結保存されていた細胞を使用するために、恒温槽等を用いて融解し、再度培養する操作のことを言う。
-
持続可能性(Sustainability)
将来にわたって現在の社会の機能を継続していくことができる仕組み。
-
消費者にとっての選択の自由(Freedom of choice for consumers)
自分がほしい商品やサービスを自由に選ぶことはできる権利のことで、これを担保するためには、提供する事業者が商品やサービスに関する情報をわかりやすく表示するなどの取組みが必要。
-
食品衛生管理者(Food hygiene manager)
食品の製造や加工を行う施設において、衛生管理の責任者となる国家資格を持った者。食品衛生法に基づき、特定の食品を製造・加工する施設では、食品衛生管理者を配置することが義務付けられている。
-
食品衛生法(Food Sanitation Act)
食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図るための法律。
-
食品添加物(Food additive)
食品の製造過程または食品の加工や保存の目的で、食品に添加・混和などの方法によって使用される物質。食品添加物の安全性について食品安全委員会による安全性評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や使用の基準を定めた上で使用が認められている。
-
食品表示法(Food Labeling Act)
食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した包括的かつ一元的な法律。
-
初代培養細胞(Primary cultured cells (Primary cells))
動物等の生体から直接採取された臓器や組織から細胞を回収し、培養を開始した細胞集団。通常は、異なるの性質を持つ細胞集団で構成されている。
-
新開発食品調査部会(Subcommittee on Novel Food Development)
食品衛生法に基づいて、消費者庁に設置された食品衛生基準審議会の調査部会で、新しい食品の安全性や有効性について科学的かつ客観的に評価し、食品衛生法に基づく規制や表示に関して審議する。
-
3Dプリンター(3D printer)
3次元データに基づいて立体物を造形する装置。細胞培養食品分野においては、細胞とゲル状の基質(バイオインク)を混ぜ合わせて、3Dプリンターに充填し、層状に積み重ねることで、立体的な組織を形成することが可能。
-
成長因子(増殖因子)(Growth factor)
特定の細胞の増殖や分化を促すタンパク質の総称。例えば、繊維芽細胞増殖因子(Fibroblast growth factor: FGF)や肝細胞増殖因子(Hepatocyte growth factor: HGF)などが挙げられる。
-
製品トレーサビリティ(Product traceability)
製品がいつ、どこで、誰によって作られたのか、その履歴を明確に追跡できる状態にすることを言う。原材料の調達から、製造、流通、販売、そして消費に至るまでの全工程において、製品に基づいた情報を記録し、必要に応じて溯って確認できるようにする仕組み。
-
セルバンク(細胞バンク)(Cell bank)
液体窒素等を用いて超低温で保存された細胞の集合体。同質の細胞を大量に調製し、冷凍保管した細胞集団を「マスターセルバンク」と呼び、マスターバンクの細胞を出発材料として、実際の製造に使用するために調製・保存された細胞集団を「ワーキングセルバンク」と呼ぶことが多い。
-
増殖因子(成長因子)(Growth factor)
特定の細胞の増殖や分化を促すタンパク質の総称。例えば、繊維芽細胞増殖因子(Fibroblast growth factor: FGF)や肝細胞増殖因子(Hepatocyte growth factor: HGF)などが挙げられる。
た行
-
種細胞(Seed cells)
細胞培養において、新たな培養を開始するために用いられる初期の細胞集団。
-
タンパク質クライシス(タンパク質危機)(Protein crisis)
地球温暖化の進行や頻発する異常気象、さらに増え続ける世界人口と新興国における食肉や養殖魚等のタンパク質資源に対する需要拡大が大きなリスク要因になっており、近い将来、タンパク質の需要が供給を上回ってしまうことに対する懸念。
な行
-
日本細胞農業協会(Cellular Agriculture Institute of the Commons)
細胞によるモノづくり”細胞農業”が、 人々の理解と信頼のもとに社会普及することをミッションに掲げて活動する非営利団体。
-
ノベルフード(Novel food)
食経験のない食品あるいは食品素材。1997年5月15日以前にEU内で人間によってほとんどあるいは全く消費されていなかった食品または食品原料を指す概念。
は行
-
バイオリアクター(Bioreactor)
細胞や微生物を用いて、目的とする物質(成長因子、抗体等のタンパク質等)や大量の細胞を生産するための装置。
-
培養液(Culture medium)
細胞の生存や増殖に必要な栄養素、成長因子、無機塩類等を含んだ液体成分。通常は、基礎培地、血清成分、成長因子等で構成されている。
-
培養上清(Conditioned medium)
細胞培養に使用した培養液のことで、細胞が分泌する様々な物質(タンパク質、代謝産物等)が含まれている。
-
培養肉(Cell-cultivated food)
動物個体等から抽出した細胞を原料とし、細胞培養の技術を用いて生産した食品素材。細胞培養食品や細胞性食品とも呼ばれることもある。
-
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)
食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法。
-
PDL(Population doubling level)
細胞の分裂回数(Population doubling level)の略語で、正常細胞は一定の分裂回数を経て老化、死滅するため、継代数より厳密な細胞履歴の管理方法として利用されている。
-
微細藻類(Microalgae)
肉眼では識別困難な大きさの藻類の総称。水中に生息する植物プランクトンで、光合成で酸素と有機物を合成することで、地球の生態系において重要な役割を担っている。
-
標準作業手順書(Standard operating procedure (SOP))
企業や組織の中で、特定の業務を遂行するための手順を標準化・文書化したもので、作業ミスを減らし、一貫した品質や安全性を確保するために使用される。
-
フィーダー細胞(Feeder cells)
目的とする細胞を培養する際に、その細胞の増殖や分化をサポートするために培養する細胞。
-
フードセキュリティ(Food security)
全ての人が、いかなる時にも、活動的で健康的な生活に必要な食生活上のニーズと嗜好を満たすために、十分で安全かつ栄養ある食料を、物理的、社会的及び経済的にも入手可能であるときに達成される状況。
-
フードテック(Food tech)
最先端の技術を駆使して食に関する社会的課題を解決し、食の可能性を広げる技術。
-
フードテック官民協議会(Public-Private Council for Food Tech)
食・農林水産業の発展と食料安全保障の強化に資する、資源循環型の食料供給システムの構築や高い食の QOL(Quality of Life)を実現する新興技術について、国内の技術基盤の確保に向けて、協調領域の課題解決の促進や新市場の開拓を後押しする官民連携の取組を推進する団体。
-
不死化細胞(Immortalized cells)
通常の細胞が一定の回数しか細胞分裂ができないのに対して、不死化細胞は無限に増殖を続けることができるようになった細胞。
-
プロテオーム解析(Proteome analysis)
細胞内や培養上清に含まれるタンパク質成分を網羅的に解析する技術。生体内に存在するタンパク質(Protein)の総体のことをプロテオーム(Proteome)と呼び、その種類や濃度を網羅的に分析する手法を「プロテオーム解析」、あるいは「プロテオミクス」と言う。
-
ヘイフリック限界(細胞分裂限界)(Hayflick limit (cell division limit))
正常な体細胞が培養条件下で分裂できる回数には限界があることを指し、通常のヒト細胞の分裂限界はおおよそ50回。
-
平面培養(Planar culture (two-demensional culture))
フラスコやウェルプレート等の平らな培養容器に細胞を接着させて培養する手法。顕微鏡を用いた細胞の観察が容易なため、細胞増殖、形態、運動性等の確認によく用いられる。
ま行
-
前培養(Pre-culture)
細胞培養食品等の生産に用いる細胞を少量から増やしたり、品質の確認を行ったりする培養工程。
-
無菌操作(Aseptic operation)
滅菌された原材料、器具、装置等を用いて、微生物の混入を完全に防ぎながら、実験や生産等の操作を行うことを言う。
-
メタボローム解析(Metabolome analysis)
細胞内や培養上清に含まれる代謝産物を網羅的に解析する技術。生体内に含まれる代謝物質の総体(すべて)を「メタボローム」と呼び(”metabolite”と”-ome”からの造語)、その種類や濃度を網羅的に分析する手法を「メタボローム解析」、あるいは「メタボロミクス」と呼ぶ。
-
滅菌(Sterilization)
物体に存在するすべての微生物を高温の水蒸気で死滅させたり、孔径の小さなフィルターで物理的に除去することで、無菌状態にすることを言う。
-
モニタリング(Monitoring)
培養工程におけるモニタリングは、細胞や微生物等を培養する工程を継続的に観察し、記録することを指し、細胞培養においては、細胞形態の観察や栄養素(特にグルコース)の消費量の記録などが挙げられる。
ら行
-
ライフサイクルアセスメント(LCA)(Life cycle assessment)
製品やサービスの“ゆりかごから墓場まで”の環境に対する負荷を見積もることによって,環境に対するイ
ンパクト(影響)を評価しようとする手法であり、LCAと呼ばれることが多い。
-
リアクター培養(Reactor culture (three-deminsional culture))
バイオリアクター等の装置を用いて、大量の細胞を培養する手法。タンパク質や抗体等の有用物質の大量生産などに用いられる。